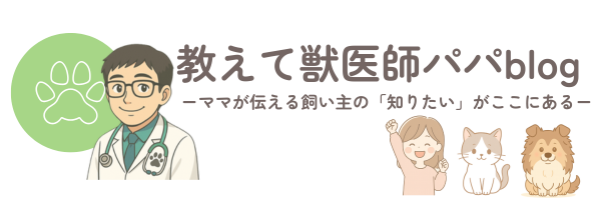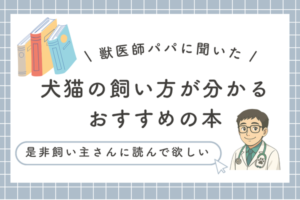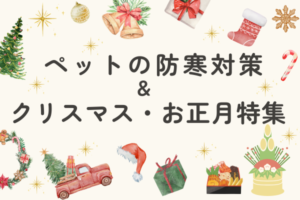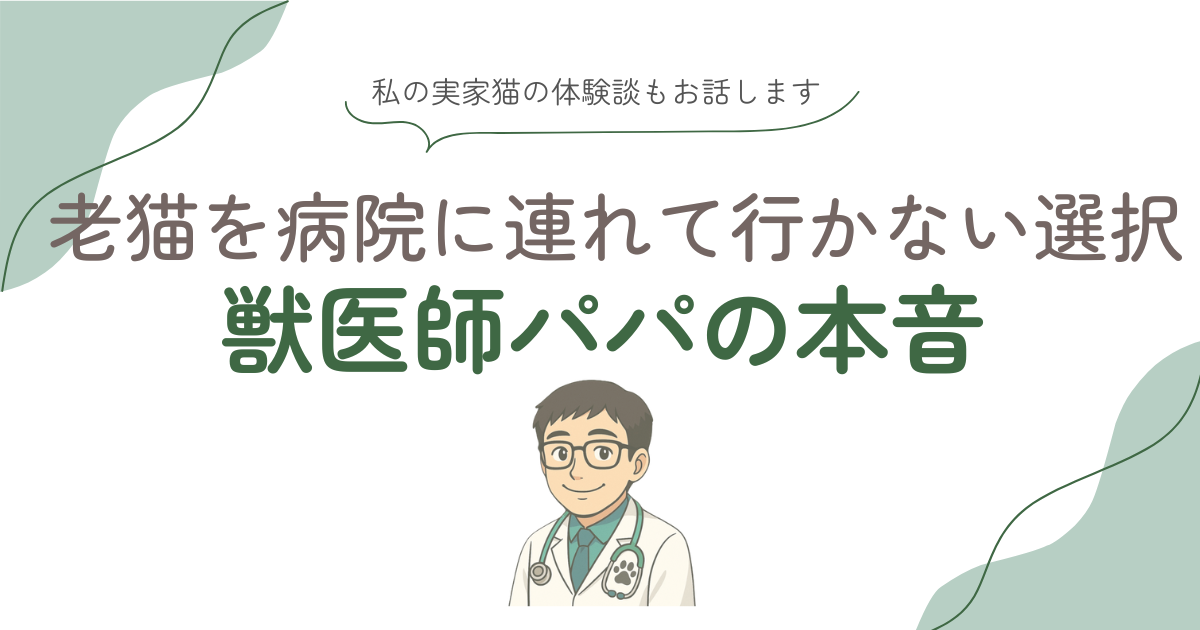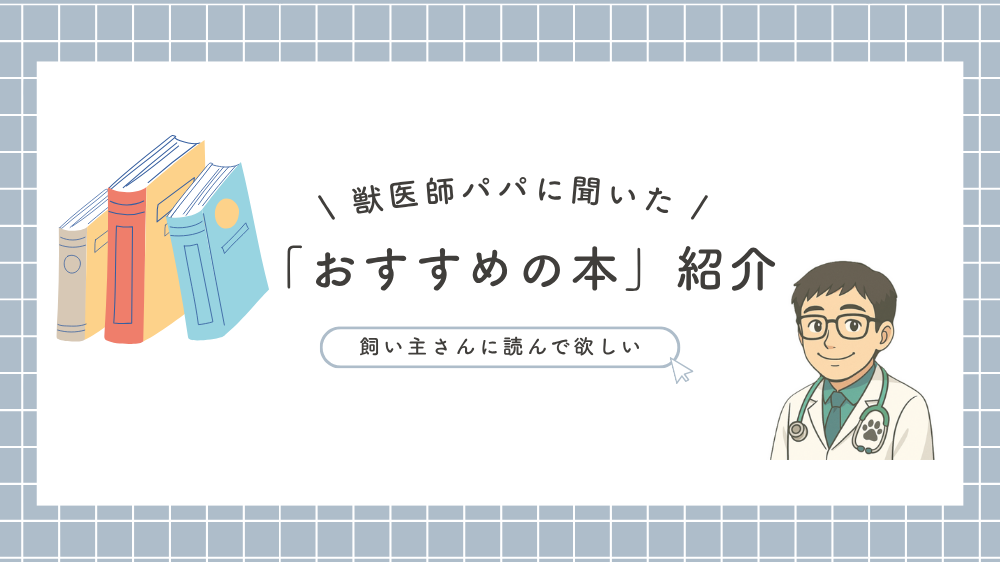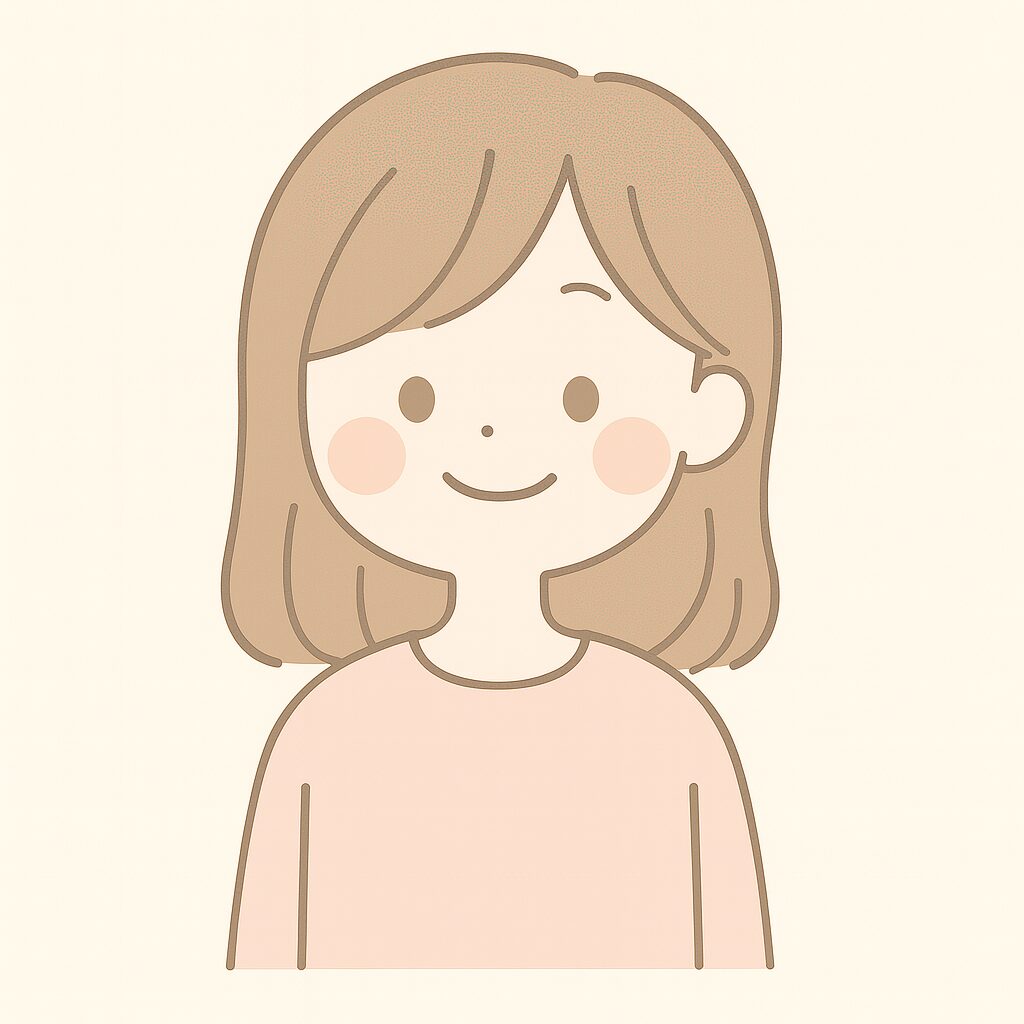うちの老猫、元気だけど病院で一度は診てもらった方がいいのかな?

病院って猫にとってストレスだし、無理に連れて行かなくてもいいのかも?
高齢になった猫を病院に連れて行くべきか…その判断に迷う飼い主さんは多いものです。

今回は、こんなお悩みを解決していきます。

こちらのポイントに沿って、お伝えしていきます。

獣医師パパ監修の元、詳しく解説しますので安心して読み進めてくださいね。
老猫を病院に連れて行かない選択はダメ?獣医師パパの本音
老猫にとって、病院に行くことは時に大きなストレスになります。
獣医師としての理想はありますが、病院に通わずとも飼い主さんと幸せに過ごしている猫ちゃんもいます。

一緒に考えていきましょう!
①健康で元気なら無理な通院は不要
- 毎年の健康診断は理想的だが、必ずしも全猫に必要ではない
- 病院に通わずとも20歳近くまで元気に暮らす猫もいる
- 食欲・排泄・動きに問題がなければ、自宅観察で十分な場合もある
猫の平均寿命
・全体:15.79歳(2010年比+1.43歳)
・外に出ない猫:16.25歳
・外に出る猫:14.18歳
特に食欲があり、排泄や動きに問題がない場合、無理に通院させる必要はないという考え方も十分に尊重されるべきだと思います。
②ストレス回避が老猫には大切
- 猫は環境変化や知らない場所が苦手
- 病院への移動・待合室・診察が三重のストレスになる
- 高齢猫では、ストレスが体調悪化や免疫低下を招くリスクがある
- 通院によって体力を消耗する場合もある
高齢猫にとって「ストレスの少ない暮らし」は健康維持の大きなカギです。
通院がかえって体調を崩すケースもあるため、必要以上に連れ出すよりも、自宅で落ち着いて過ごせる時間を優先することが大切です。
③自宅でできるケアを整える
- 栄養バランスの取れた食事を意識する
- 水分補給を促すため、水皿を複数設置する
- 寝床やトイレを常に清潔に保つ
- スキンシップを通して体調変化を観察する
- 爪切り・ブラッシングなどの基本ケアも継続する
通院せずとも、毎日の生活習慣を整えることで老猫の健康を支えることは可能です。
愛猫のリズムに合わせ、ストレスを与えずにケアすることが、長生きの秘訣になります。
④家族で話し合うことが大事
- 「病院に連れて行くかどうか」は家族で共有しておくべきテーマ
- 猫の性格・持病・介護体制を考慮して方針を決める
- いざという時の判断を迷わないよう、事前に意見をすり合わせておく
- 最期の迎え方についても、穏やかな選択を話し合っておく
老猫の医療方針には“正解”がありません。
だからこそ、家族で対話しながら「その子らしい最期」を一緒に考えることが大切です。
早めの話し合いが、後悔のない時間をつくります。
老猫を病院に連れて行くべき症状の見極め方

高齢になると、猫の体調変化はゆるやかで分かりにくくなります。
「少し元気がない」「寝てばかりいる」など、日常のちょっとした違和感を見逃さないことが大切です。
ここでは、通院が必要なサインと、自宅で様子を見てもよいケースを整理していきましょう。

特に以下のポイントは注意深くチェックしておきましょう。
| 観察ポイント | 注意したい変化例 |
|---|---|
| 排泄の様子 | 尿の量が減った・便秘・血尿など |
| 食欲の変化 | 食べる量の減少・好きなものを拒否 |
| 行動パターン | 動かない・寝てばかり・隠れるなど |
| 呼吸・歩き方 | 呼吸が荒い・歩き方がおかしいなど |
老猫の通院が必要なサイン
- 食欲が数日間まったく戻らない
- 体重が短期間で明らかに減ってきた
- 嘔吐や下痢が2日以上続いている
- 尿が少ない、または血尿が見られる
- 呼吸が荒い・速い、咳が続く
- 歩き方がふらつく・立ち上がれない
- 触れると痛がる、鳴き声が変化した
- 元気がなく、反応が鈍い・隠れて出てこない
これらのサインが見られたら、できるだけ早めに受診を検討しましょう。
老猫は体調を隠す傾向があるため、“なんとなくおかしい”と感じた時点で相談することが早期発見につながります。

何か異変があった際は、病院に連れて行ってあげましょう。
老猫の様子を見てもよいケース
- 食欲・排泄・動きが普段どおり安定している
- 一時的な食べムラ(気温や湿度の影響など)
- 毛玉を吐いた後の軽い嘔吐1〜2回
- 眠る時間が増えたが、起きれば反応は良い
- 軽いくしゃみや咳が1日で落ち着いた
これらは老化による自然な変化や、環境の一時的な影響であることが多いです。
慌てず、2〜3日間は様子を観察してみましょう。
その間、食事量や排泄の回数、体重などをメモしておくと、後に病院へ行く際にも役立ちます。
老猫を病院に連れて行かない選択をした実家猫の体験談

私の実家には18歳になる老猫がいます。
その猫の体験談を少しお話しようと思います。
私が小学生の頃、同級生が捨て猫として拾い、里親募集をきっかけに実家猫と出会いました。子猫時代にはワクチンや去勢手術のために通院しましたが、それ以降は病院に行くことなく、穏やかに年を重ねてきました。
それ以降初めて病院に連れて行ったのが、今年のお正月です。母から「足から血が出ている、引きずって歩いている」と連絡があり、夜間の救急病院を受診しました。診察の結果、爪が長く伸びてしまい、それが肉球に刺さったことによる出血と痛みでした。幸い軽症でしたが、老猫になってから初めての受診でした。
この出来事をきっかけに、家族で「今後もし命に関わる何かがあったらどうするか?」という話を真剣にするようになりました。
私たちの結論は「今まで通り穏やかに過ごせているのなら、無理に病院に行く必要はないよね。もし、最期を迎える時期が来て苦しそうなら、その苦しみを取ってあげるために病院には行こう」というものでした。
この体験を通して感じたのは、老猫と暮らす家族にとって、最期の迎え方を話し合っておくことはとても大切だということです。病院に行く・行かないという判断に、正解はありません。でも、話し合うことで「自分たちにとっての正解」を見つけられるのだと思います。
老猫を病院に連れて行かない時のホームケアのポイント

ここからは、愛猫が安心して暮らせる環境を整える上での、ホームケアのポイントについてお伝えします。
①重要:老猫の脱水対策
- 老猫は腎臓の働きが低下しやすく、体内の水分を維持する力が弱くなる
- 飲水量の減少は、腎不全や便秘などのリスクを高める
- ウェットフードやスープタイプのごはんを取り入れる
- 水皿を部屋の複数箇所に置き、飲みやすい位置に設置する
- フィルター付きの循環式給水器も効果的
軽い脱水でも被毛のパサつきや便秘などのサインが出ることがあります。
「水を飲む回数」「尿の量」「便の硬さ」を定期的にチェックし、変化に気づけるようにしましょう。
②老猫には暖かく静かな場所の確保
- 体体温調整が難しくなり、冷えや暑さの影響を受けやすい
- 冬は床からの冷気対策を、夏は直射日光とエアコン風を避ける
- 猫ベッドの下にペットヒーターやブランケットを敷くと快適
- 騒音・振動・人の出入りが少ない静かな空間を確保する
老猫は「いつもの場所」で安心します。
模様替えや家具の移動は最小限にとどめ、生活リズムが乱れないように整えることがストレス軽減につながります。
③寝たきりや介護状態でも清潔・快適を保つ
- 長時間同じ姿勢になると、床ずれや皮膚炎が起きやすい
- 吸水シーツ・防水マットを併用して常に乾燥を保つ
- 体を支えながらやさしく拭く「部分清拭」で衛生を保つ
- ブラッシングで血行促進・毛玉予防にも効果的
介護期の猫は、清潔さ=快適さ=健康寿命に直結します。
寝たきりでも、声かけや撫でるスキンシップを忘れず、心の安心感も一緒にケアしてあげましょう。。
④猫用ケアグッズを上手に取り入れる
- 老猫専用フード・サプリメント:関節や腎臓ケアに特化した商品を選ぶ
- 床ずれ防止マット:体圧を分散して皮膚を守る
- 段差を減らすスロープ:ジャンプや昇降時のケガ防止に
- トイレ:出入りしやすい浅めタイプを選ぶ
「便利グッズ」は老猫の生活を支えるサポートツールです。
すべて揃える必要はありませんが、その子の性格・体調に合わせて取り入れることで、通院しなくても快適な毎日を送ることができます。
\あわせて読みたい/
まとめ:老猫と穏やかに過ごすためにできること
老猫を病院に「連れて行かない」ことは、愛情や思いやりに基づいた立派な選択肢のひとつです。
大切なのは、猫にとっての幸せや安心を最優先に考え、無理のない方法で関わっていくこと。
理想は毎年健診をして早期発見に努めることかもしれませんが、現実的には通院がストレスになることも多く、無理に病院へ連れて行くことが“愛情”になるとは限りません。
私たち家族も獣医師であるパパと一緒に、「その子らしく生きること」を大切にしています。
愛猫と過ごせる時間を、なるべく優しく穏やかに包んであげましょう。