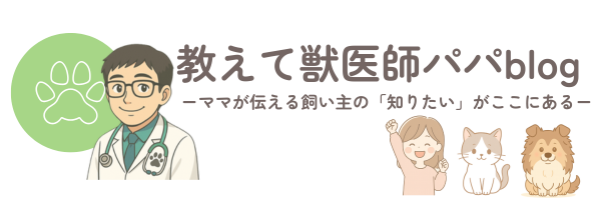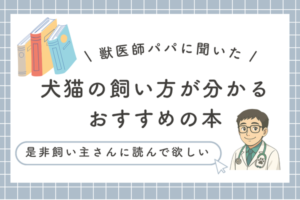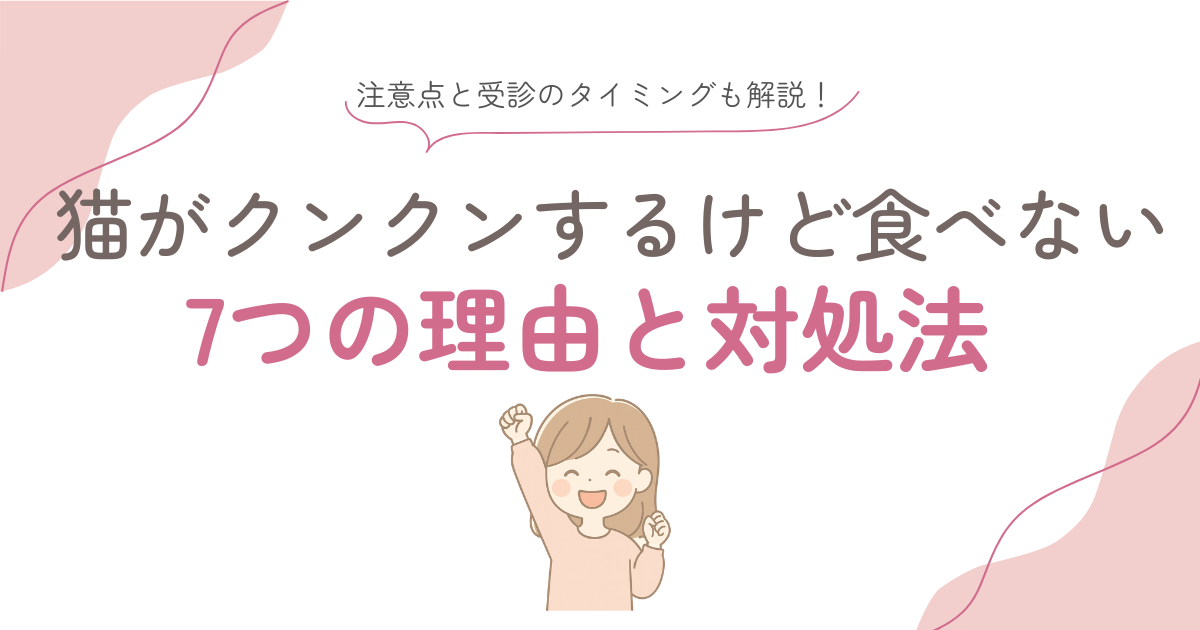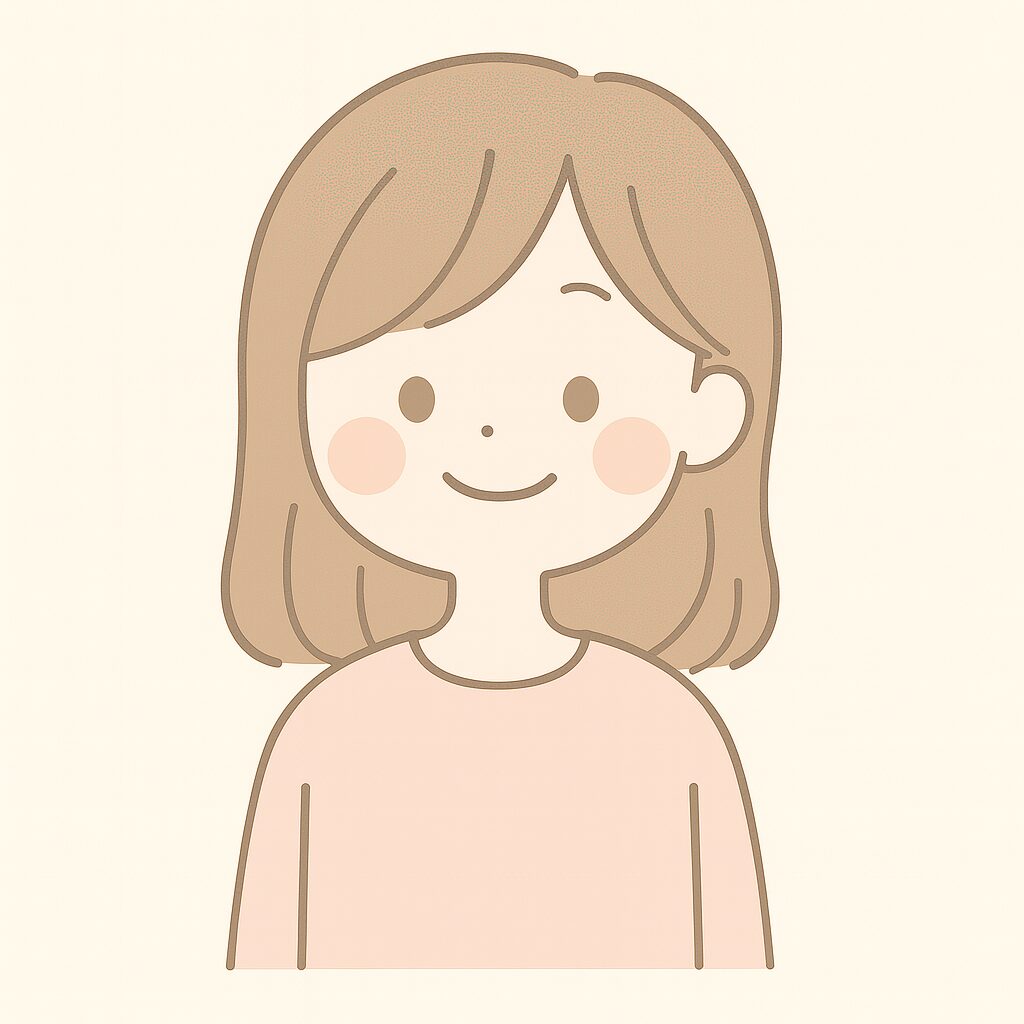ごはんを出してもクンクンするだけで食べないの。体調悪いのかな…?

おやつは食べるのにごはんは無視される。飽きただけ…?
猫って、ちょっとした変化で食欲が落ちることも多いんですよね。

こんなお悩みを解決していきます。

こちらのポイントに沿って、お伝えしていきます。

獣医師パパ監修の元、詳しく解説しますので安心して読み進めてくださいね。
猫がクンクンするけど食べない7つの理由と対処法まとめ
猫が「匂いをクンクンと嗅ぐけど食べない」行動には、いくつか考えられる理由があります。
まずは全体像を把握して、愛猫の行動を冷静に見守りましょう。

一緒に勉強していきましょう!
猫が食べない理由
①食事の匂いや味に飽きている
猫は同じ味に飽きやすい動物です。ずっと同じフードだと「またこれ?」と興味を失ってしまうことがあります。
ローテーションで味や食感を変えることで、食いつきが改善されることも少なくありません。
とくに人工香料の少ないナチュラル系フードは、風味が淡く飽きやすい傾向もあります。
猫が食べない理由
②フードの鮮度や温度が悪い
冷蔵庫から出したばかりのフードや、空気に触れて酸化したドライフードは、匂いが立ちにくく魅力が半減します。
食事は常温に戻して、香りを引き出してから与えるのがおすすめです。
また、湿気の多い時期はドライフードでもカビ臭くなることがあるため、保管方法も重要です。
猫が食べない理由
③おやつの食べすぎ&お腹が空いてない
おやつは少量でも高カロリーなものが多く、猫の空腹感を奪ってしまうことも。
ごはん前におやつを与える習慣がある場合は、一度見直してみましょう。
おやつが主食代わりになってしまうと、栄養バランスも崩れやすくなります。
猫が食べない理由
④環境の変化によるストレス
猫は非常に繊細で、引っ越し・模様替え・来客など、ちょっとした環境の変化がストレスになることがあります。
安心して食事できる静かな空間を意識してあげましょう。
猫が食べない理由
⑤病気や体調不良のサイン
食欲はあるけど食べないという場合、口内炎や内臓疾患が隠れていることも。
数日間続く場合や他の異常(嘔吐・下痢など)がある場合は、早めに獣医の診察を受けましょう。
特にシニア猫では、腎臓や歯のトラブルが原因のことが多いです。

歯のトラブルを抱えた、猫ちゃんは意外と多いんです!
猫が食べない理由
⑥年齢による食欲や好みの変化
シニア期に入ると嗜好が変わり、これまでのフードを受け付けなくなるケースも。
柔らかめの食事や、香りの強いウェットフードに切り替えて様子を見ましょう。
どうしても、年齢とともに嗅覚や味覚も鈍くなるため、食に対する興味が薄れやすくなります。
猫が食べない理由
⑦食器や置き場所が気に入らない
猫は食器の形状や素材、食事の位置にこだわりを持つことがあります。
滑りやすい器や、壁際すぎる配置がストレスになっている可能性もあります。
金属の反射や匂いを嫌がる猫も多く、陶器やガラス製に変えると食べ始めることもあります。
猫がクンクンするけど食べない時の対処法5選
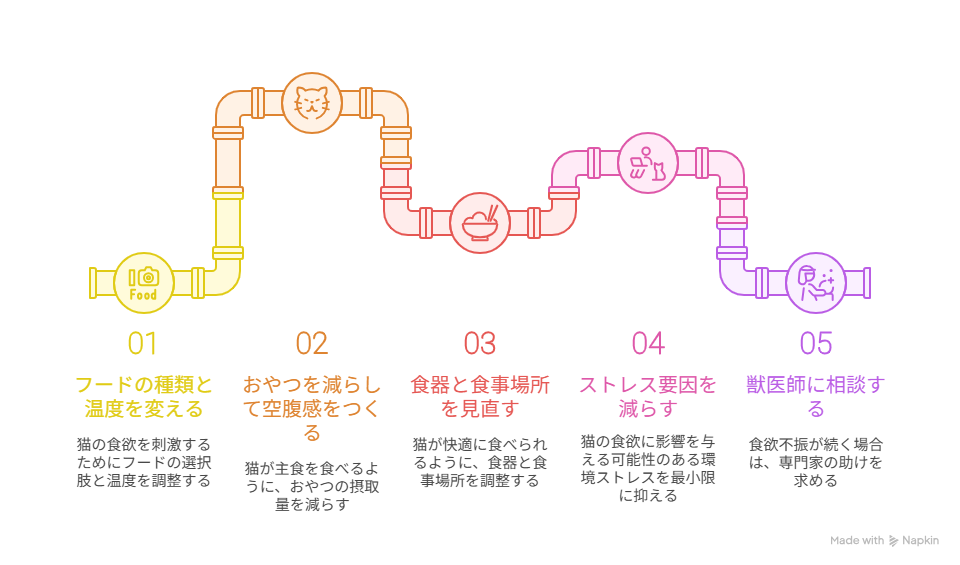
それぞれの原因に対して、すぐに試せる対処法を紹介します。
無理に食べさせようとせず、猫のペースを尊重しながらケアしていきましょう。
猫が食べない時の対処法
①フードの種類や温度を変えてみる
飽きや鮮度の問題には、フードのローテーションや温め直しが効果的です。
特にウェットフードは、電子レンジで数秒加熱するだけでも香りが立ち、猫の食欲を刺激します。
また、素材や味に変化を加えることで「初めてのもの」に反応して食いつきが戻ることがあります。
猫が食べない時の対処法
②おやつを減らして空腹感をつくる
高カロリーなおやつを頻繁に与えていると、猫が主食を食べなくなることがあります。
1日のおやつ量を見直し、メリハリのある与え方を心がけましょう。
特に食事前1〜2時間は何も与えず、「お腹が空いた状態」でごはんを出すのがポイントです。
猫が食べない時の対処法
③食器や食事場所を見直す
猫は食器の材質・形・高さに敏感です。たとえば、金属製の器は匂いや反射で嫌がることもあります。
安定感のある陶器やガラス製の食器、高さを調整できる台座付きの器がおすすめです。
また、落ち着ける静かな場所に食事スペースを確保し、他のペットや人通りが少ない位置に移してみましょう。
猫が食べない時の対処法
④ストレス要因を減らす
猫は環境の変化に敏感で、食欲にも大きく影響します。来客・模様替え・大きな音などがあると、警戒して食べなくなることも。
安心できる寝床や食事場所を整え、生活リズムが崩れないように配慮することが大切です。
フェロモン製品(フェリウェイなど)を使ってリラックス効果を与えるのも有効です。
猫が食べない時の対処法
⑤2日以上続いたら獣医師へ相談を
長期間の絶食(48 時間以上)は、腸絨毛の萎縮、消化管機能の回復の遅れ、栄養失調や腸内細菌の異常、さらに肥満の猫では肝リピドーシスなどの問題の発生につながるため、避ける必要があります。
食欲不振が続くときや、元気がない・吐く・下痢をしているなど他の症状がある場合は、すぐに受診しましょう。
猫がクンクンするけど食べない時の注意点
猫が食べない時に獣医師に相談すべきタイミング
上記3つのポイントに、1つでも当てはまる場合は、早急に病院を受診しましょう。

他にも「食べない」以外にいつもと違うサインがないか観察しましょう。
猫が食べない時の注意点
①水の飲み方やトイレの様子
水分摂取と排泄の状態は、体内の健康状態を反映する重要なサインです。
猫が急に水を飲まなくなった、水を飲む量が極端に増えた、トイレの回数が減った・増えた・長時間こもるなどの変化がある場合、腎臓病や膀胱炎、尿路結石などの病気が潜んでいる可能性があります。
猫が食べない時の注意点
②甘える・隠れるなど行動の変化
普段とは違う甘え方や行動パターンの変化も、重要なサインです。
また、目つきがぼんやりしている、呼んでも反応が薄い、動きが鈍くなっているなどの変化も要注意。

「なんかいつもと違う」と思ったら、それは体や心のSOSかもしれません。
猫が食べない時の注意点
③遊ぶ元気はあるか
遊びへの反応は、猫の「元気のバロメーター」です。
「遊ばない+食べない」が同時に見られるときは、迷わず獣医師に相談を。
猫がクンクンするけど食べない時のQ&A
猫の「食べない」行動には、いくつもの背景があり、一見似た行動でも理由が異なることがあります。
ここでは飼い主さんからよくあるケース別の疑問を、具体的な解説とあわせてお答えします。
Q1:猫に手であげるとご飯を食べるのはなぜ?
A:猫は飼い主との信頼関係が深い動物なので、直接手からもらうことで安心感が生まれ、食べることがあります。
ただし、手からしか食べなくなるクセがつくと、自力で食事をしなくなり、将来的にストレスや問題行動の原因になることも。
あくまで一時的な方法として使い、徐々に器からの食事に戻すように誘導しましょう。
Q2:朝は食べるのに夜はクンクンだけで食べない理由は?
A:時間帯によって食べない場合は、気温・空腹感・活動量の差などが関係していることが多いです。
たとえば、朝は寝起きで空腹感が強く、涼しい時間帯なので食欲が出やすいのに対し、夜は部屋が暑かったり、日中におやつを食べていたことでお腹が満たされている可能性も。
このような場合は、夜の環境を見直したり、夕食前のおやつを控えるなど、生活リズム全体を整えてあげることが大切です。
Q3:猫が食後に砂をかけるような仕草は?
A:猫がフードボウルのまわりを引っかくようにする仕草は、本能的な「埋める・片づける」行動の一種です。
また、これは「もういらない」「気に入らない」といった意思表示でもあり、特に嫌いな匂い・味のフードを与えた時に出やすい傾向があります。
こうした仕草が頻繁に見られる場合は、そのフードが猫に合っていない可能性もあるため、種類を変えたり、食事環境を見直すサインとして受け止めましょう。
まとめ:猫がクンクンするけど食べない時は何かしらのサインがある
猫がクンクンするけど食べないのは、好みの問題やちょっとした不快感であることが多いです。
しかし、長引く場合や行動の変化があるときは、病気のサインかもしれません。
日々の小さな変化に気づけるよう、しっかり観察することが何よりのケアになります。