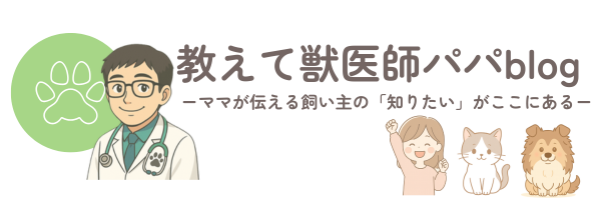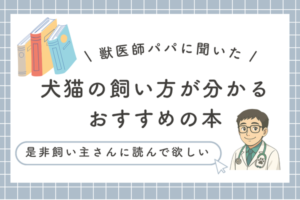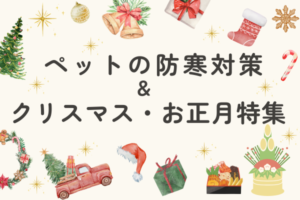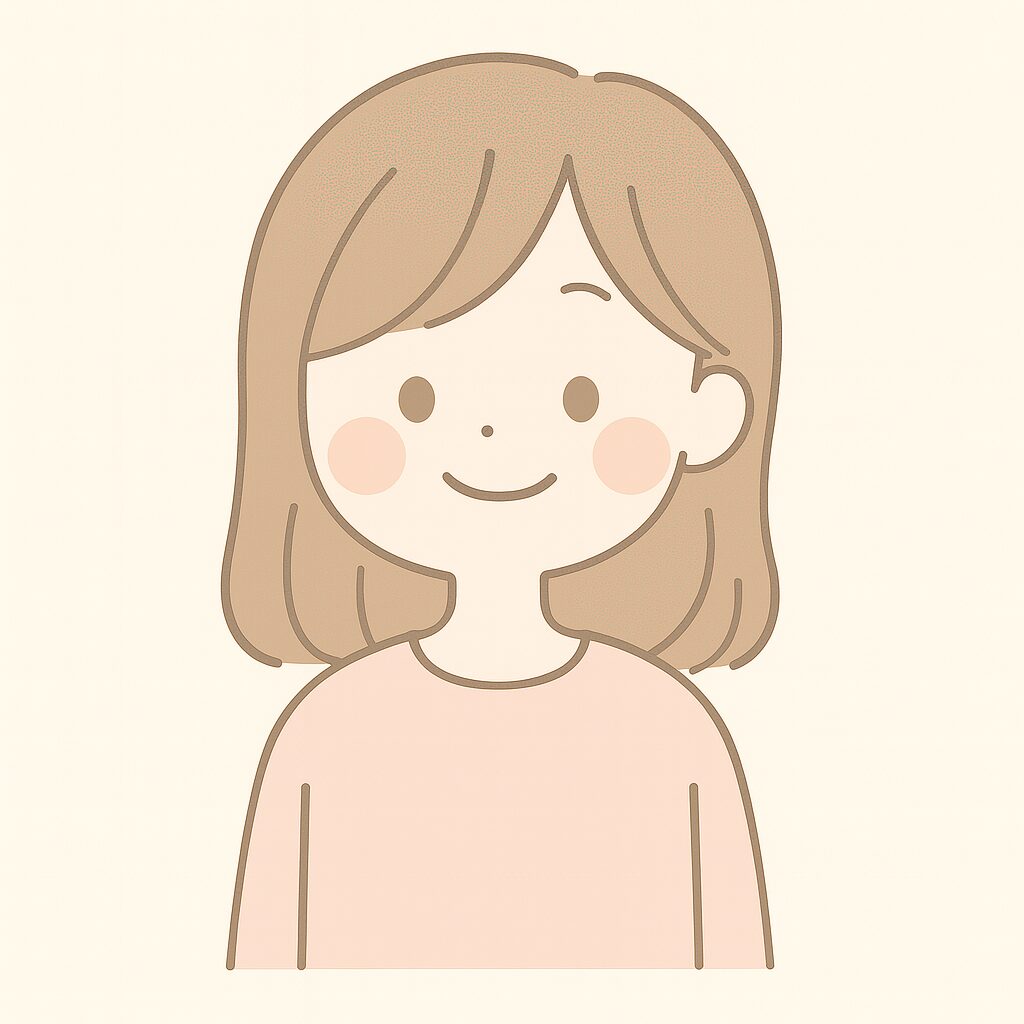猫が布団で粗相する癖がついちゃって…もう大変なんです。

洗濯が凄く大変…でも、猫自身もストレスで粗相しちゃうのかな…
猫の粗相問題は、飼い主さんが悩まされる大きな問題ですよね。

今回は、こんなお悩みを解決していきます。

こちらのポイントに沿って、お伝えしていきます。

獣医師パパ監修の元、詳しく解説しますので安心して読み進めてくださいね。
猫が布団で粗相する問題|治った理由と7つの実践対策
猫の粗相問題に悩まされている飼い主さんは、思った以上に多いんですよね。
私の妹が最近お迎えした2匹目の猫ちゃんは、奮発して買ったソファに粗相してしまうそうです…。
粗相問題を経験している飼い主さんからすると、「…わかる!!!」という場面ばかりだと思います。

猫の粗相対策は「即効性」と「継続性」がポイントとなります。
さっそく対策から分かりやすく解説していきますね。

一緒に学んでいきましょう!
布団の粗相対策
①トイレ環境の最適化を徹底
猫が布団に粗相する原因のひとつが、「トイレが気に入らない」こと。
- トイレの数を「猫の数+1個」に増やす
- トイレ掃除を1日1〜2回行い、常に清潔を保つ
- 週1回は猫砂を全交換+トイレ容器を丸洗いする
- 猫砂の種類(素材・粒の大きさ)を変えてみる
- トイレの設置場所を静かで落ち着ける場所に変更する
中でも猫砂の種類変更は効果が出やすい対策のひとつ。
まずはトイレ周りを見直し、猫にとって「ここが一番落ち着ける排泄場所」になるよう、環境を整えてあげましょう。
布団の粗相対策
②布団を物理的にガード
猫は柔らかくて飼い主の匂いが残る場所を「安心できる排泄場所」として認識してしまうことがあります。
- 布団を使っていない時間は押し入れなどに収納する
- 防水シーツやビニールカバーで布団を保護する
- 寝室のドアを閉めて猫の立ち入りを制限する
- 布団の上に荷物を置いたり、シーツの素材を変えて違和感を与える
そのため、視界から布団を消す・触れられない状態にすることが効果的。
防水カバーでガードすれば被害の軽減にもなりますし、違和感を与えることで「ここではできない」と学習させやすくなります。
粗相の再発を防ぐためにも、まずは「猫が布団にアクセスできない環境」を作ることが基本対策になります。
布団の粗相対策
③ストレス・健康要因を確認
猫の粗相には、環境ストレスや体調不良が関係していることも。以下の点をチェックしてみましょう。
- 最近引っ越しや模様替え、来客など環境の変化があった
- 他の猫や赤ちゃんなど、新しい存在が加わった
- 排尿の回数が増えている、血尿などの症状がある
- 遊ぶ時間やスキンシップが減っていないか見直す
- 粗相の頻度が高い場合はすぐに動物病院で相談する
粗相は、単なる“しつけの失敗”ではなく、猫からのSOSサインであることも多いです。
生活環境の変化によってストレスを感じたり、泌尿器の不調(膀胱炎・結石など)を抱えていたりする場合も。
また、フェリウェイなどの猫用フェロモン製品や、遊び時間を増やすことも、ストレス軽減に効果的です。
布団の粗相対策④
布団を出しっぱなしにしない
猫が布団に粗相する習慣を断つには、「寝室と布団の管理」が重要です。次の対策を取り入れてみましょう。
- 布団を使わないときは毎回収納する
- 猫が自由に出入りできないように寝室のドアを閉める
- 寝室の環境を見直し、猫が落ち着けない空間にする
- 布団の置き方・場所を定期的に変えて「ここはトイレじゃない」と認識させる
布団がいつも同じ場所に広げられていると、猫にとって「排泄してもいい場所」と学習されやすくなります。
特に夜間以外は布団を畳んでおく、部屋への出入りを管理するなど、環境を工夫してみましょう。
布団の粗相対策
⑤粗相後のニオイを完全除去
猫の「ここはトイレだ」と思わせるきっかけは、“残ったニオイ”です。再発を防ぐために以下の対策を行いましょう。
- 猫用の酵素系クリーナーでニオイを分解する
- 重曹やクエン酸と併用して消臭力をアップさせる
- 一般的な洗剤ではなく、猫専用の消臭剤を使う
- 粗相した場所はできるだけ早く処理する
- 布団ごと洗うか、洗えない場合はクリーニングに出す
猫の嗅覚は人間の何倍も鋭く、私たちには気づけないわずかな尿のニオイでも、猫にとっては「ここがトイレ」と判断する大きな要因になります。
洗剤や香料でごまかしても意味がなく、ニオイ成分そのものを分解・除去することが必須。
特に酵素系クリーナーは尿中のたんぱく質を分解してくれるので、猫の粗相には最適です。
\あわせて読みたい/
わざとじゃない!猫の布団で粗相が治った理由

猫の粗相には、明確な“きっかけ”や“理由”があります。決してわざとやっている訳ではないのです。
ここで、粗相とスプレー行動の違いも確認しておきましょう。
スプレー行動とトイレ以外で排泄する粗相は、似て非なるものです。スプレー行動は、多くの場合立ったまま、壁やカーテンのような垂直面に対して、少量のおしっこをします。普段のおしっこを凝縮したように強烈なニオイがするのもスプレー行動の特徴です。
出典:みんなの子猫ブリーダー>猫のマーキングやスプレー行動ってなに? 粗相との違いや原因、対策法をご紹介します

それでは、実際に治った事例から、原因と対策考えていきます。
①トイレが合わなかった猫
- いつの間にか猫砂を変えたのが原因で、布団で粗相するようになった
- 以前使っていた砂に戻したら、すぐに粗相が止まった
- トイレの位置も落ち着かない場所だったため、静かな場所に移動して改善
猫によって好みのトイレ環境はさまざまです。
変化に気づきにくいこともありますが、実は“合わない砂”や“落ち着かない場所”が原因のことも。変えてみる価値は大いにあります。
②布団に安心感を感じていた猫
- 布団が柔らかくて飼い主の匂いがついているため、安心して排泄してしまっていた
- 防水シートで質感を変え、寝室も出入り禁止にしたことで改善
- 粗相後に残ったニオイをしっかり消臭することもポイント
布団は「安心する場所」でもあるため、トイレとの境界が曖昧になる猫も。
環境の一部を見直すだけで、排泄場所の認識がリセットされることがあります。
③環境ストレスや体調不良が原因だった猫
- 引っ越し後に突然粗相が始まり、病院で軽い膀胱炎と診断された
- フェリウェイ(猫用フェロモン)を使い、安心できる空間作りと投薬で改善
- 飼い主が一緒に遊ぶ時間を増やすことで精神的な安定が得られた
猫は変化に敏感な動物。身体的な不調と精神的な不安が重なって粗相につながるケースもあります。
適切な治療とストレスケアの両方が必要になります。
猫の粗相で汚れた布団の洗い方とニオイ対策
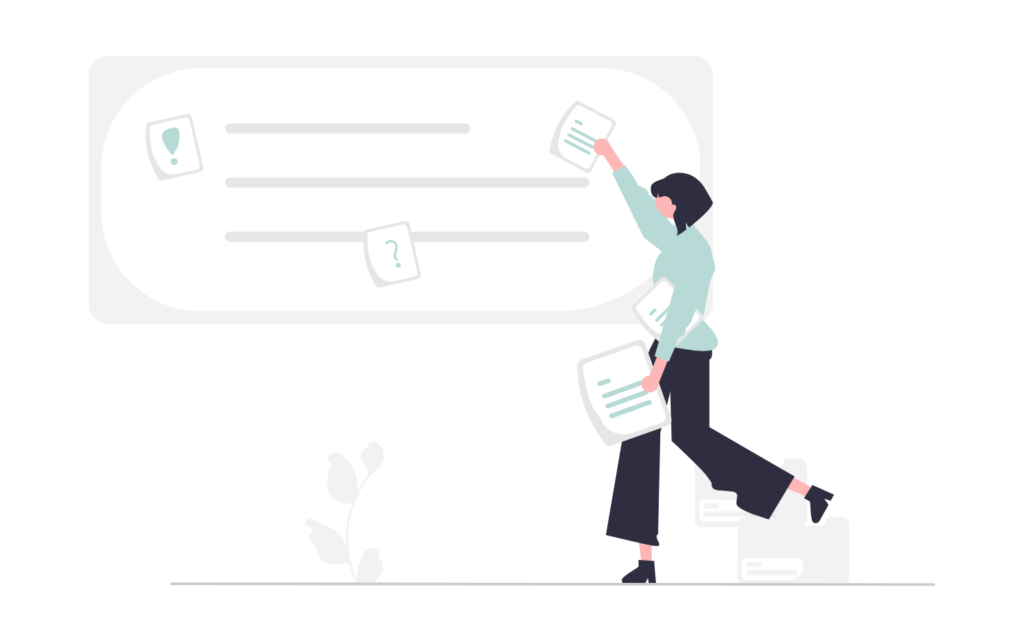
粗相された布団の処理を間違えると、再発のリスクが高まります。
正しい洗い方とニオイ除去の手順を知っておきましょう。
| 手順 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ①ある程度汚れを取る | 水分を素早く吸収 | タオルやペーパーで押さえるように吸い取る。擦らないこと |
| ②すぐに洗浄開始 | 酵素系洗剤や重曹で分解 | 尿の成分を分解するには酵素系洗剤が最適。重曹と併用で効果UP |
| ③完全に乾燥 | 丸洗い or 業者依頼 | 自宅で洗えない布団はプロに任せる。天日干しで完全乾燥を |
| ④消臭対策 | 消臭スプレーを使用 | 布団自体の匂い予防と、次の粗相を防止する目的で使用する |
乾燥が不十分だとニオイが再発したり、カビの原因になることも。
処理は素早く、確実に行うことが大切です。
【Q&A】猫の粗相に関するよくある悩み
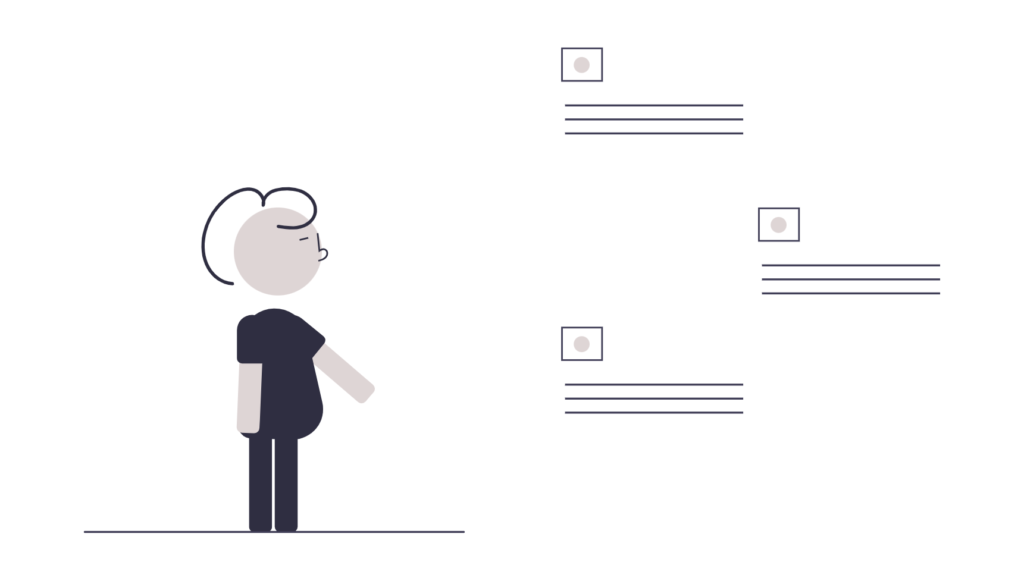
最後に、実際によくある飼い主さんの疑問をQ&A形式で解説していきます。
Q1:猫から布団を守る方法はある?
A:物理的に布団をカバーするのが一番効果的です。
防水シートやビニールカバーで包んだり、使用後はすぐに収納することで再発を防げます。
寝室自体に猫を入れないのも有効な手段です。
Q2:猫の粗相はわざと…?
A:猫は「わざと」ではなく、何かしらの不満やストレス、体調の変化を伝えるために粗相をします。
叱るよりも原因を探ることが改善の近道です。
Q3:猫の粗相がもう限界です。
A:何度も続く粗相は本当に辛いですよね。でも必ず原因があります。
獣医師や猫の行動学の専門家に相談することで突破口が見つかるケースも多くあります。ひとりで抱え込まないでくださいね。

粗相問題だけでの受診だと、行きにくい方は、健康診断を受ける際に「本当に困っている」と相談してみると良いかもしれません。
Q4:猫が突然布団に粗相するようになった原因は?
A:急な粗相には、環境の変化や体調不良が隠れている可能性があります。
引っ越しや新しい家族、模様替えの影響を見直し、同時に健康チェックも行いましょう。
まとめ:猫の粗相問題は根気と試行錯誤が大切
猫の布団での粗相は、原因さえ見つかれば改善できます。
すぐできる対策を組み合わせ、根本原因に気づくことが大切です。
焦らず続けていけば、必ず“治った!”と感じられる日が来ます。