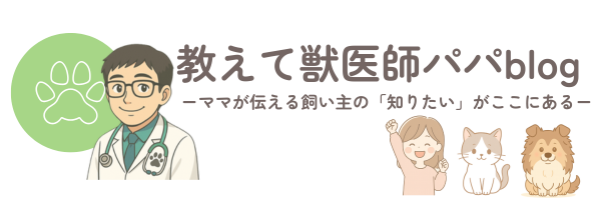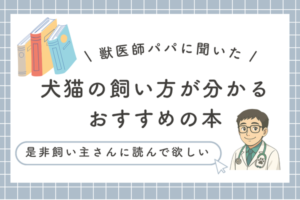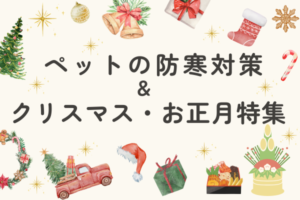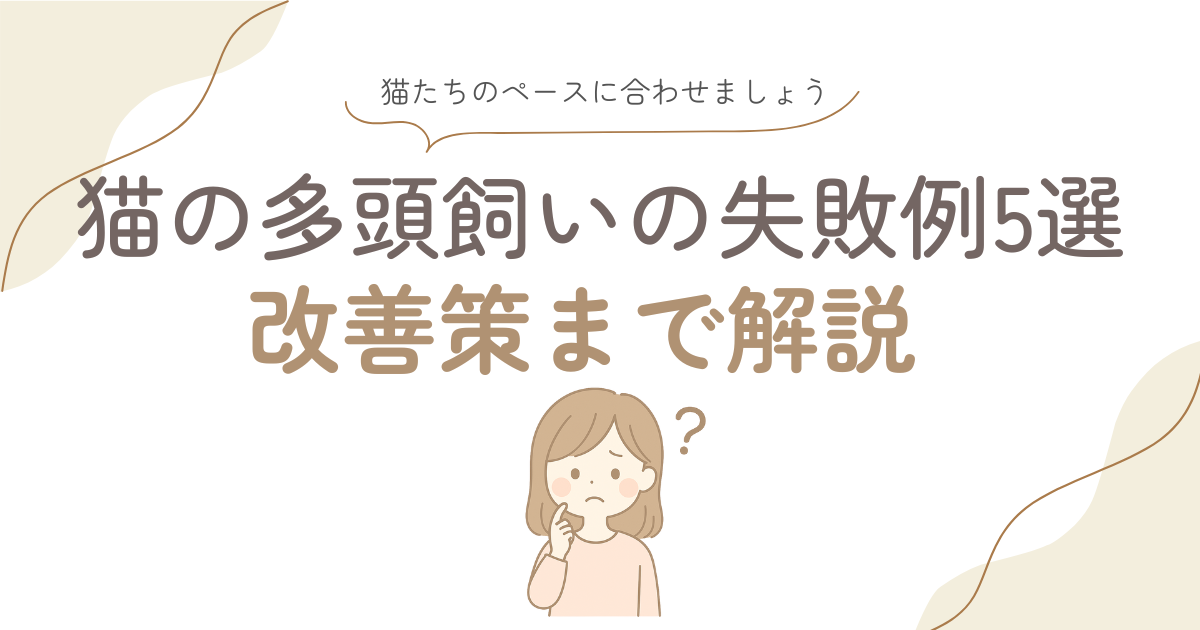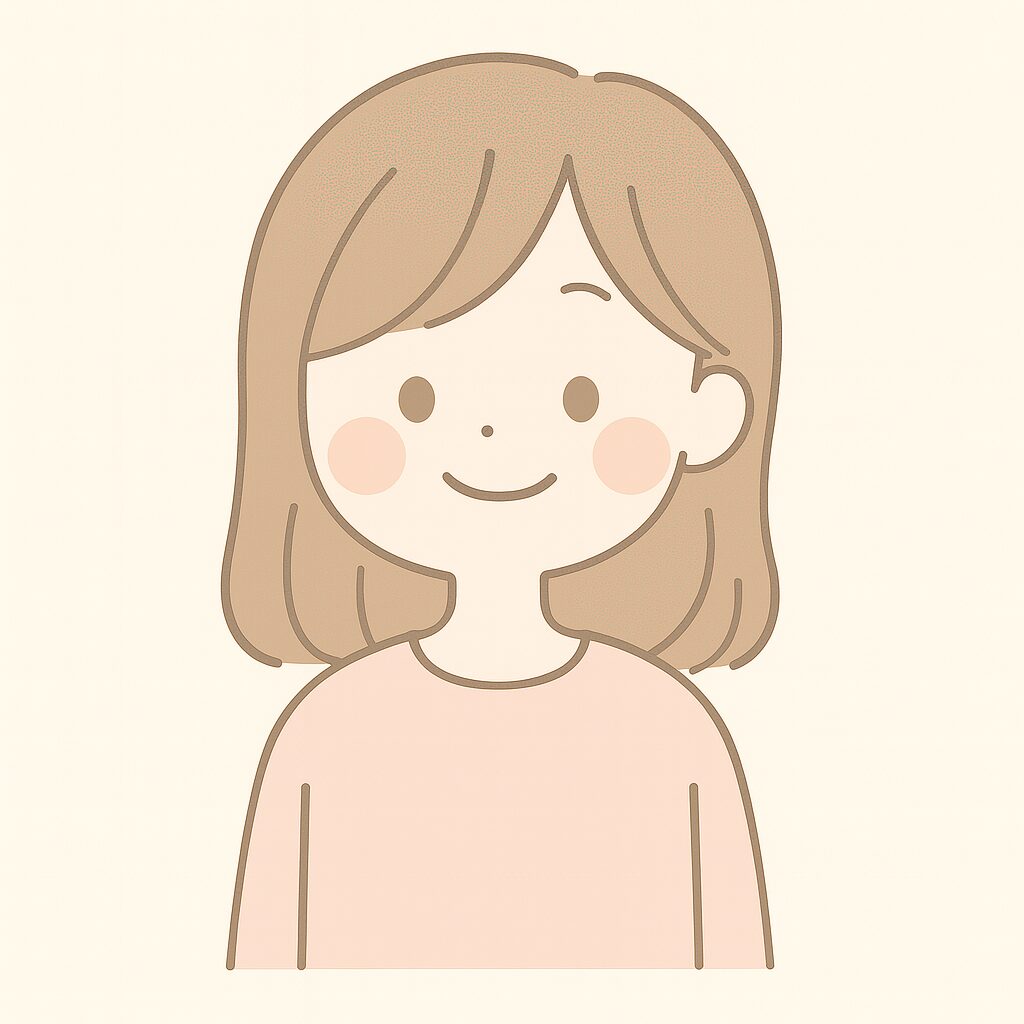猫の多頭飼いの失敗例を聞いてみたい!

実は、わが家も二匹目のお迎えを迷ってるんだけど、失敗例を先に知りたいな。
多頭飼いは、理想と現実のギャップに戸惑いますよね。

今回は、こんなお悩みを解決していきます。

こちらのポイントに沿って、お伝えしていきます。

獣医師パパ監修の元、詳しく解説しますので安心して読み進めてくださいね。
猫の多頭飼いの失敗例5選!獣医師パパが改善策まで解説
猫の多頭飼いでよく見られる失敗例をまとめました。
「なぜうまくいかないのか」が明確になることで、次に取るべき行動も見えてきます。

一緒に失敗例を見ていきましょう!
猫の多頭飼いの失敗例
①即時同居で威嚇・ストレス
- いきなり同じ空間に入れてしまった
- 先住猫が威嚇・攻撃を繰り返すようになった
- 新入り猫が隠れて出てこなくなった
新入り猫を迎えた際に、導入ステップを踏まずに同居を開始すると、先住猫が「侵入者がきた」と警戒心をむき出しにしてしまいます。
この初対面の印象が悪いままだと、敵対関係が長期化し、仲良くなるチャンスを失ってしまうことがあります。

僕は大切にして欲しい事は、「先住猫ファースト」の気持ちです。
猫の多頭飼いの失敗例
②トイレや食事トラブル
- トイレの数が足りず粗相が増えた
- ごはんや水を取り合って喧嘩になる
- 落ち着ける寝床がなく、どちらかが遠慮してしまう
猫にとってトイレや食器は「自分専用であるべきスペース」。
それを共有させてしまうと、使用のタイミングや場所をめぐって争いになりやすくなります。
静かな場所に分散配置されていないと、使いたくても使えずストレスが溜まり、喧嘩や体調不良につながります。
猫の多頭飼いの失敗例
③年齢差や性格の不一致
- 子猫がしつこく遊ぼうとして高齢猫が疲弊
- 怖がりな猫が強気な猫に押されて引きこもる
- お互いに距離を取り続けて関係が発展しない
猫にも相性があります。年齢差や性格の違いを考慮せずに迎えると、生活リズムや空間の使い方が合わず、どちらかがストレスを感じやすくなります。
相性が悪い場合、猫たちが常に緊張状態で暮らすことになり、飼い主の負担も増えてしまいます。
猫の多頭飼いの失敗例
④発情期トラブル
- 発情期になると攻撃的になった
- マーキングや大声での鳴き声が増えた
- 喧嘩が頻繁に起こるようになった
去勢・避妊がされていない猫は、ホルモンの影響で行動が大きく変わります。
多頭飼いでは、発情期に入った猫の存在が他の猫に刺激を与え、喧嘩やストレスの原因になります。
去勢や避妊の手術を受ける時期は、生後6ヵ月頃、初めての発情期を迎える前が理想です。
ほとんどの病院では、予防接種が終わっていること、ダニやノミ、お腹の寄生虫の駆除が終わっていることなどを条件としているため、発情期を迎えてから慌てないようにしましょう。

お迎えする猫の年齢も様々だと思いますが、去勢は・避妊は早めに済ませた方が良いです。
猫の多頭飼いの失敗例
⑤飼い主の対応が逆効果
- 喧嘩した猫を大声で叱った
- 無理やり一緒に遊ばせようとした
- 仲裁のつもりで一方を隔離・排除した
猫に対して人間の価値観で感情的に接すると、逆に信頼関係が壊れてしまうことがあります。
「叱ればわかる」「仲良くしなさい」は通用しません。
猫同士の関係は繊細で、飼い主の無意識の対応が悪化を招くケースもあるのです。
\あわせて読みたい/
猫の多頭飼いの失敗例を踏まえた改善策5選

ここからは、上記の失敗例を踏まえた「実践的な改善策」を紹介します。
環境整備や導入方法、飼い主の関わり方を少し見直すだけで、猫たちの関係は大きく変わることがあります。
改善策①段階的導入で関係を築く
新入り猫を迎えるときは、いきなりの対面を避け、猫同士が安心できるステップを踏むことが重要です。
焦って仲良くさせようとすると、逆効果になることが多いため、以下の流れで段階的に関係を築いていきましょう。
| ステップ | 内容 | 補足ポイント |
|---|---|---|
| 1. 隔離する | 新入り猫を別室に | まずは環境に慣れさせる。数日〜1週間が目安 |
| 2. 匂い交換 | タオルやおもちゃを交換 | お互いの存在を“間接的”に認識させる |
| 3. ドア越し対面 | 姿が見えるようにする | 軽い反応が見られる程度でOK |
| 4. ケージ越し対面 | 安全に近距離で対面 | 短時間・穏やかな様子を見て判断 |
| 5. 直接対面 | 監視下で少しずつ慣らす | 威嚇がないことを確認して時間を延ばす |

ポイント: 無理に仲良くさせないこと。猫のペースを最優先し、信頼関係をゆっくり築くのが成功のコツです。
改善策②「猫の数+1」用意する
個人スペースを分けることで、猫たちが安心して使える空間が確保され、ストレスや衝突のリスクを軽減できます。
| 必要な資源 | 推奨数 | 補足 |
|---|---|---|
| トイレ | 猫の数+1個 | 静かな場所・複数箇所に設置 |
| 食器・水飲み場 | 各猫1つずつ以上 | できるだけ距離をとる配置に |
| 寝床・隠れ場所 | 各猫1か所以上 | 高低差のある場所や箱型も効果的 |
\あわせて読みたい/
改善策③相性・年齢・性格を見極める
猫同士の相性や年齢差は、多頭飼いのトラブルを防ぐための重要なチェックポイントです。
- 先住猫の性格を見極める
→ 怖がり・神経質なタイプなら、おっとりした性格の猫が合いやすい。
→ 社交的・好奇心旺盛な猫には、活発な子も受け入れやすい。
- 年齢差がある場合は空間を分ける
→ 子猫は運動量が多く、高齢猫は静かに過ごしたい傾向あり。
→ 同じ部屋で生活させず、行動エリアを分ける工夫を。
- 仲良くできなくても共存はできる
→ 無理に近づけず、距離を保って暮らせばOK。
→ 別々の寝床やトイレで、それぞれが落ち着ける環境を整える。

相性を軽視して迎えると、どちらかが我慢を強いられ、ストレスや不仲が長引く原因になってしまいます。
改善策④ホルモントラブルを防ぐ
発情期の猫は行動が不安定になり、多頭飼いでは喧嘩の原因になりやすいです。
- 去勢・避妊手術を行う(獣医師と相談のうえ)
- 発情期の行動変化を観察し、ストレスが出そうな環境要因を減らす(静かな場所・同じ性の猫の組み合わせなど)
- マーキングしやすい家具・壁などを保護し、清潔を保つ
改善策⑤飼い主の接し方を見直す
猫は繊細な生き物です。「人間の正義感」で怒るのではなく、冷静な観察と対応が鍵です。
- 猫のストレスサイン(耳の向き・尻尾・隠れる・グルーミング過剰など)をしっかり観察
- 叱るのではなく、望ましい行動を強化(おやつ・褒め言葉など)
- 無理に接触させるのではなく、距離を保ちつつ安全に過ごせる環境を整える
【Q&A】猫の多頭飼いに関するよくある悩み

最後に、実際によくある飼い主さんの疑問をQ&A形式で解説していきます。
Q1:猫の多頭飼いはやめたほうがいい?
A:猫たちが明らかに強いストレスを感じている、飼い主のケアが難しくなっている場合は「無理しない決断」も大切です。
ただし、やめるのではなく「環境改善」や「空間分離」で続けられるケースもあります。
Q2:猫の多頭飼いは後悔するって本当?
A:「準備不足」「性格の不一致」「時間が足りない」などが原因で後悔する人はいます。
しかし、逆に「仲良くなってくれて本当に良かった」という声も多く、事前の対策と継続的な観察がカギとなります。

ちなみに私の妹は、最近二匹目の猫をお迎えして、とても幸せそうです。
猫大好き家系なので、羨ましくなりますね。
Q3:猫の二匹目のお迎えで後悔した理由は?
A:よくある理由は、「先住猫との相性が悪かった」「手間が倍増した」「ケンカばかりで疲れた」といったものです。
2匹目を迎える前に、先住猫のストレス耐性や性格をしっかり把握することが重要です。
Q4:2匹目の猫を隔離できない時は?
A:完全な隔離ができない場合でも、ケージ・パーテーション・家具の配置で物理的距離を作ることができます。
匂いの交換と、接触時間を短くコントロールすることで徐々に関係性を築くことは可能です。
まとめ:猫たちの平和な共存には「準備と理解」がカギ
猫の多頭飼いで失敗する原因の多くは、「準備不足」と「猫同士の相性を軽視」したことにあります。
焦らず、猫たちのペースに合わせて、少しずつ信頼関係を育んでいきましょう。
きっと、穏やかに寄り添う猫たちの姿が見られるはずです。