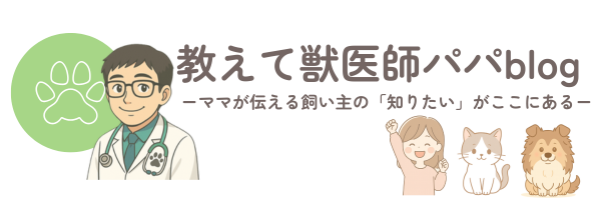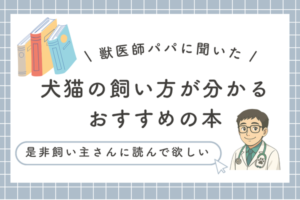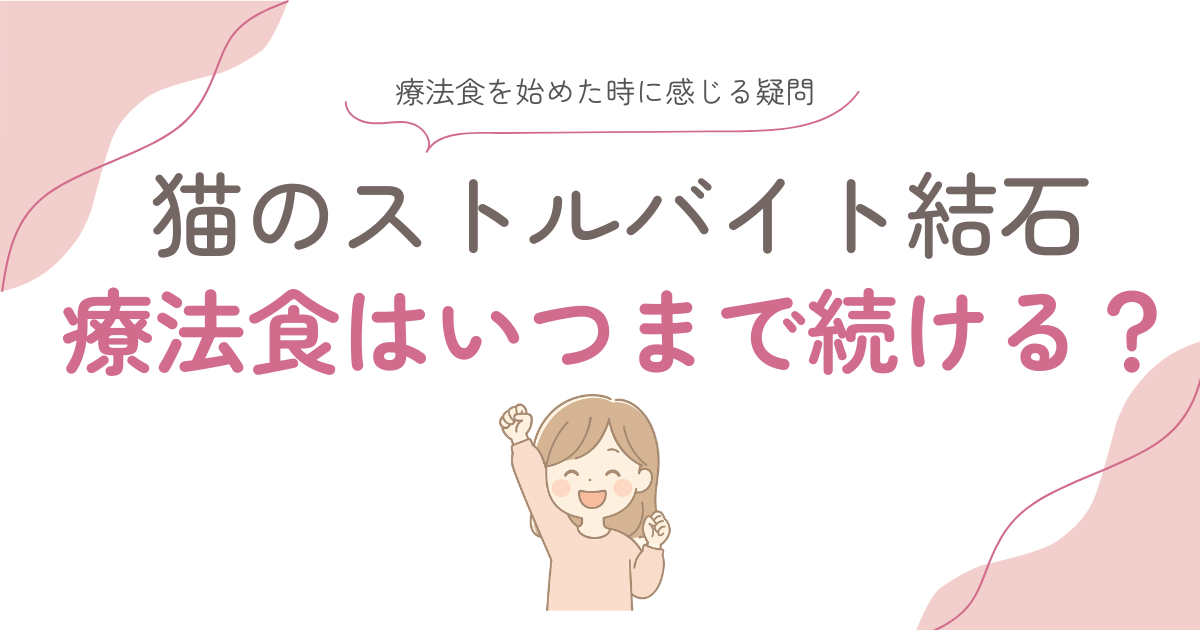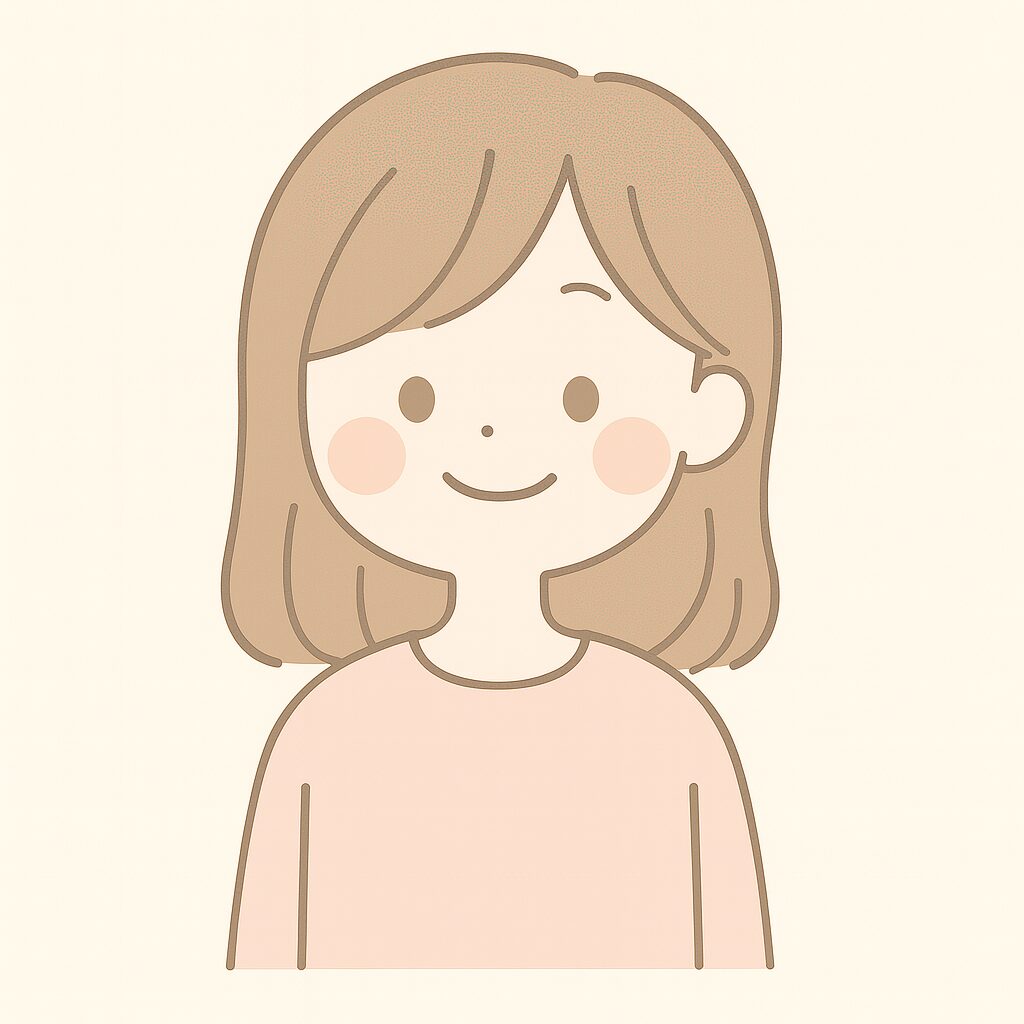猫の尿結石の療法食って、いつまで続けるの…?

しばらく続けてね…って言われたけど、結構高いんだよな。
獣医師への相談の仕方もお伝えしてきますね。

ストルバイト結石に限らず、猫の療法食は「いつまで続ければいいの?」と悩む飼い主さんは多いでしょう。
今回は、こんなお悩みを解決していきます。

こちらのポイントに沿って、お伝えしていきます。

獣医師パパ監修の元、詳しく解説しますので安心して読み進めてくださいね。
猫のストルバイト結石の療法食はいつまで続けるべき?

ストルバイト結石を経験した猫にとって、療法食は「一時的な治療」か「継続すべき予防対策」か、状況によって異なります。
ここでは、その判断基準を4つに分けて解説します。

一緒に学んでいきましょう!
猫の尿路結石の療法食はいつまで?
①初発なら最低2〜3ヶ月
- 初めてストルバイトを発症した猫は、2〜3ヶ月は療法食の継続が基本
- pH値の安定と結晶の消失を確認する必要がある
- 尿検査を定期的に行い、治療効果を把握する
短期間で改善が見られることも多いですが、「治ったように見える」だけで再発するケースもあります。
病院によって、尿検査の間隔は異なると思いますが、必ず再検査を受けましょう。
猫の尿路結石の療法食はいつまで?
②結晶が消え再評価後に終了
- 結晶が消えてpHが正常範囲(6.0〜6.5)に安定したら見直しのタイミング
- 通常の総合栄養食ではなく、移行期用フードへの段階的切り替えが安全
- 急な切り替えや自己判断は再発リスクを高める
尿のpHは、犬猫ともに6.5前後が理想的とされています。
酸性(5.5/6以下)またはアルカリ性(7/7.5以上)に傾くと、細菌や結晶、結石の形成に好都合な環境になり、わんちゃん猫ちゃんの健康に悪影響を与える可能性があります。
一生続けなければいけないケースは少数派。
適切な管理と段階的な食事の調整で、猫のQOLを保ちつつ再発防止が可能です。
再評価の尿検査で問題なければ(尿結晶の存在も認めない)、療法食を必ず続ける必要はなくなります。
猫の尿路結石の療法食はいつまで?
③再発歴ありなら継続推奨
- ストルバイト結石を繰り返している猫は、療法食を長期的に継続する必要あり
- 泌尿器に不安を抱えている場合も、予防のために療法食の継続が望ましい
- 療法食の種類を変える、フレーバーを変えるなどの工夫も可能
継続に抵抗がある場合もありますが、結石が再発するたびに猫の負担と医療費が増えるため、長期視点で考えることが大切です。
猫の尿路結石の療法食はいつまで?
④療法食は治療食、代替も検討可
- 療法食は医療目的で設計されており、pH調整とミネラル管理が徹底されている
- 一部には長期維持や予防用のラインも存在する
- 市販の泌尿器ケアフードに移行できる場合もある(要獣医師相談)
経済的な負担や猫の好みによる問題がある場合は、獣医師と相談しながら、より現実的な代替策を探すのがベストです。

正直、療法食は値段が高いんですよね。
「金銭的に…」と相談して頂けると、獣医師も無理な継続は勧めません。
\あわせて読みたい/
猫のストルバイト結石と療法食について学ぼう

ストルバイト結石について正しく理解することが、再発を防ぐ第一歩です。
なぜ結石ができるのか、どんなタイプがあるのかを確認していきましょう。
猫のストルバイト結石ってどんな病気?
ストルバイト結石は、リン酸アンモニウムマグネシウムが尿中で結晶化してできる結石で、特に猫に多く見られる尿路トラブルの一つです。
適切な治療をせずに放置すると、尿路閉塞や腎臓病へ進行する可能性もあり、注意が必要です。
| 主な症状 | 特徴・備考 |
|---|---|
| 排尿困難 | トイレに何度も行くのに尿が出ない、時間が長い |
| 血尿 | ピンク〜赤色の尿が出る場合がある |
| 頻尿 | 少量の尿を何度もする(痛みがあることも) |
| お腹を触られるのを嫌がる | 膀胱に痛みがあるサイン |
| トイレ以外での粗相 | 我慢できずに失敗してしまうことがある |
| 元気・食欲の低下 | 痛みや不快感によるストレスが原因になることも |
ストルバイト結石は初期症状が分かりづらく、トイレの変化や行動パターンで気づくケースが多いため、日常的な観察がとても大切です。

一度、発症したあとは上記の項目を日頃から観察してあげましょう。
猫の尿路結石には種類がある
| 結石の種類 | 尿のpH傾向 | 特徴 |
|---|---|---|
| ストルバイト | アルカリ性 | 食事での改善が可能 |
| シュウ酸カルシウム | 酸性 | 食事では溶けず、手術が必要な場合も |
| 尿酸アンモニウム | 中性〜酸性 | まれに見られ、特定の体質が関係 |
| シスチン結石 | 酸性 | 遺伝的要因が強く影響 |
尿路結石の原因が、ストルバイト結石であれば、療法食で溶かすことが可能です。
一見同じような症状でも、結石の種類によって対策が真逆になることもあるため、正しい診断が最優先です。
猫のストルバイト結石の原因は?
- 水分摂取量が少なく、濃縮された尿になる
- ミネラルバランスの偏り(マグネシウムやリンなど)
- 運動不足やストレスによる排尿回数の低下
- 尿のpHがアルカリ性に傾いている
食事だけでなく、日々の生活環境が大きく影響します。
猫のストルバイト結石の予防策は?
- 自動給水器やウェットフードで水分摂取を増やす
- 複数のトイレを清潔に保ち、使いやすい場所に設置する
- ストレスを減らす(多頭飼いなら空間の見直しも)
- 定期的な尿検査や健康診断で早期発見
- 栄養バランスのとれた食事を続ける
小さな配慮の積み重ねが、猫の体に大きな違いを生みます。
生活全体を見直すことで、ストルバイトの予防は確実に強化できます。

清潔な水分とトイレ環境は、予防対策で非常に重要です!
\あわせて読みたい/
猫の療法食ってなに?役割を正しく理解
ストルバイト結石と診断された際、多くの動物病院で勧められるのが「療法食」です。
これは治療目的で設計された特別なフードであり、一般的なキャットフードとは次のような点で異なります。
- 尿pHを弱酸性に保つことで、ストルバイト結晶の形成を防ぐ
- ミネラル(特にマグネシウム・リン・カルシウム)の含有量が調整されている
- 水分を多く摂れる設計(ウェットタイプも豊富)で、尿を薄めて排出を促す
- 腎臓や膀胱に配慮された栄養バランスが整っている
療法食は「薬のように使うフード」とも言える存在です。
与え方や切り替えのタイミングは必ず獣医師の指導を受ける必要があります。
一方で、「治ったのにずっと同じ療法食を続けている」ことによって、別の健康リスクを招いてしまう可能性があるという点も見逃せません。

現在の食事が適しているのか、定期検査の継続が大切です。
Q&A:猫のストルバイト結石に関するよくある質問

最後に、実際によくある飼い主さんの悩みをQ&A形式で解説していきます。
Q1:猫のストルバイト結石が全然治らないのはなぜ?
A:原因の特定が不十分だったり、療法食が猫に合っていない可能性があります。
水分量や生活環境も影響するため、食事以外の見直しも必要です。
Q2:猫のストルバイト結石は再発しやすい?
A:再発率は比較的高いです。特に食事管理が不十分だったり、水分摂取が少ない場合は注意が必要です。
長期的なケアが重要です。
Q3:猫のストルバイト結石で食べてはいけないものは?
A:高マグネシウムの食品(海産物中心の食事やおやつ)や人間の食べ物は避けましょう。
総合栄養食以外を与えるとバランスが崩れやすくなります。
Q4:ストルバイト結石の猫は療法食だけしかダメなの?
A:基本的には療法食のみで管理するのが原則ですが、状態が安定すれば市販の泌尿器ケアフードへの移行も検討可能です。
必ず獣医師と相談してください。
Q5:猫がストルバイト結石の療法食を食べない時は?
A:フレーバーの違う製品に切り替えたり、ぬるま湯で香りを引き出す工夫も有効です。
どうしても食べない場合は、同様の機能を持つ他製品に変更を検討します。
まとめ:猫の療法食の期間は、再発リスクが重要
猫のストルバイト結石における療法食の継続期間は、「状態の変化」と「再発リスク」によって判断されます。
初発で改善が見られれば、切り替えの検討も可能ですが、再発を繰り返す猫には継続が必要です。
大切なのは「いつまで?」ではなく、「今の食事が合っているか?」という視点。
獣医師と二人三脚で、愛猫にとってベストな食事管理を見つけていきましょう。