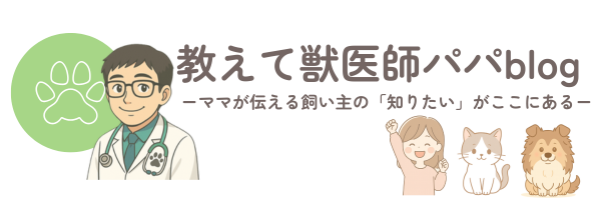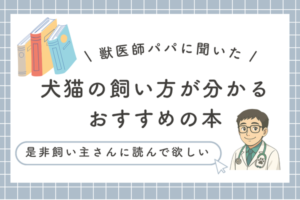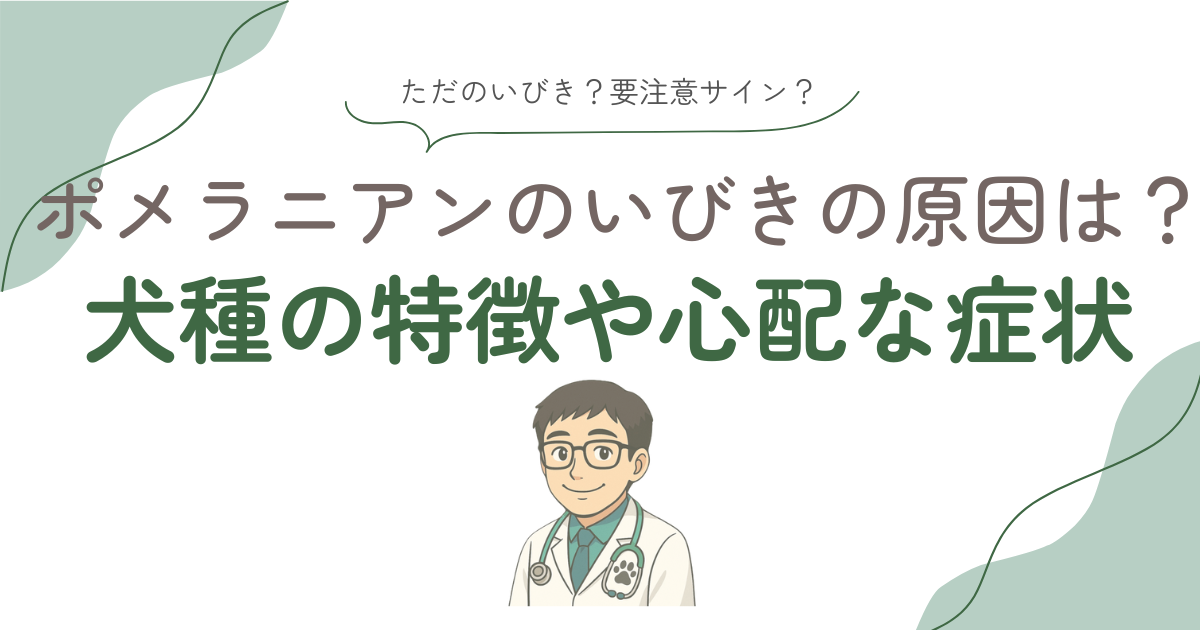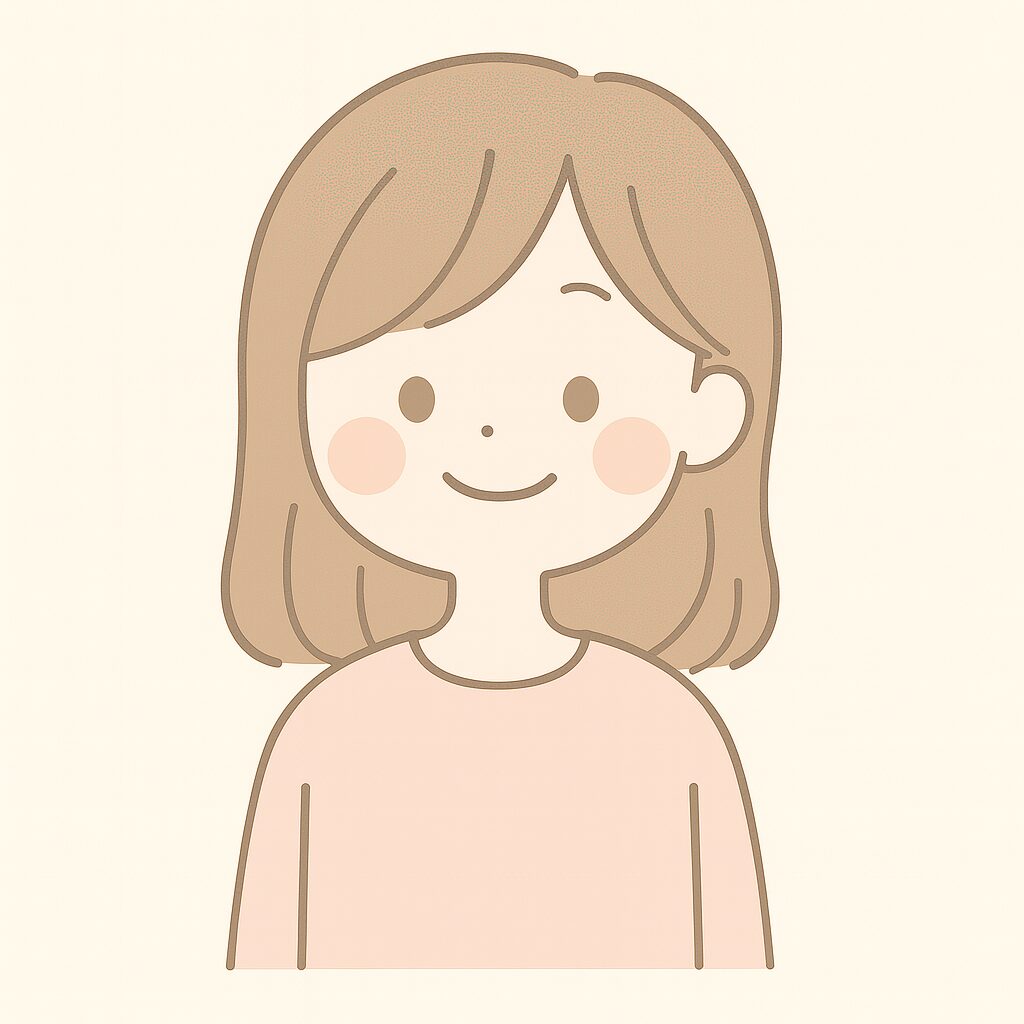うちのポメラニアン、夜によく“ブー”って音がするんだけど…大丈夫?

いびきをかきやすい犬種もいるの?
いびきは程度を超えると心配になりますよね。

今回は、こんなお悩みを解決していきます。
あなたの愛犬が“ただのいびき”か“要注意サイン”か見極める手助けにしてください。

こちらのポイントに沿って、お伝えしていきます。

獣医師パパ監修の元、詳しく解説しますので安心して読み進めてくださいね。
ポメラニアンのいびきの原因は?かきやすい犬種や心配な症状
犬も人間と同じように、寝ているときに気道が部分的に狭まればいびきをかきます。
しかし、原因には構造上のものから病気を含むものまで幅広くあります。
特にポメラニアンなど小型犬では注意点も多いため、丁寧に解説していきます。

一緒に学んでいきましょう!
原因①解剖構造差が最大の要因
- 短頭種(パグ、フレンチブルなど)は骨格的に鼻腔・気道が狭い
- 軟口蓋が長いと、空気の通り道を塞ぎやすい
- 外鼻孔狭窄、気管の変形など複合的に見られることも
- 「短頭種気道症候群」という複数の構造異常の総称が存在
短頭種の犬達・・・・フレンチ・ブルドッグ、ボストン・テリア、ボクサー、パグ、シーズー、チベタン・スパニエル、チャウチャウ、 狆(ちん)、ブルドッグ、ペキニーズ、ブリュッセル・グリフォン、キングスチャールズ・スパニエルなど
ポメラニアンは、いわゆる“典型的な短頭種”には分類されませんが、マズル(鼻先〜口元)の長さが短めで、気道構造に“余裕が少ない”小型犬という点で、似た傾向を一部持っています。
原因②肥満が気道圧迫を増強
- 首まわりに脂肪が付くことで気道が狭まる
- 呼吸の負担が増して、胸郭の動きも制限
- 体重が重い犬ほど、いびきが強くなりやすい
肥満は呼吸機能全体に負荷をかけるため、いびきの根本対策として体重管理はとても大切です。

犬も人間と一緒なんですね。
原因③呼吸器炎症で粘膜腫脹
- アレルギー性鼻炎やウイルス感染で粘膜が腫れる
- 鼻水や鼻詰まり→口呼吸→いびきの発生に
- 慢性化すると、粘膜が厚くなり持続的にいびきを助長
一時的な炎症でも、いびきは強くなることがあります。
風邪やアレルギーの時期は要注意です。
原因④加齢で筋力低下が影響
- 咽頭・喉まわりの筋肉が衰える
- 軟組織の支持力が落ち、垂れ下がりやすくなる
- 高齢になると、以前はなかったいびきが目立つことも
老化現象によって現れるいびきは、進行がゆるやかな場合が多く、他の病気と併存していないかが重要なチェックポイントです。
原因⑤気管虚脱・腫瘍に要注意
- 気管が潰れる「気管虚脱」は小型犬に多く見られる
- ガーガーという音、乾いた咳、呼吸困難などがサイン
- 鼻・咽頭・喉頭部の腫瘍が気道を塞ぐケースもあり
重篤な原因が潜む可能性もあるため、いびきに加えて他の異常が出てきたら早めの受診が必要です。

「苦しそう」という点も、重要な見分けポイントになります!
\ポメラニアンのおすすめ記事/
いびきをかきやすい犬種、ポメラニアンの特性と注意点
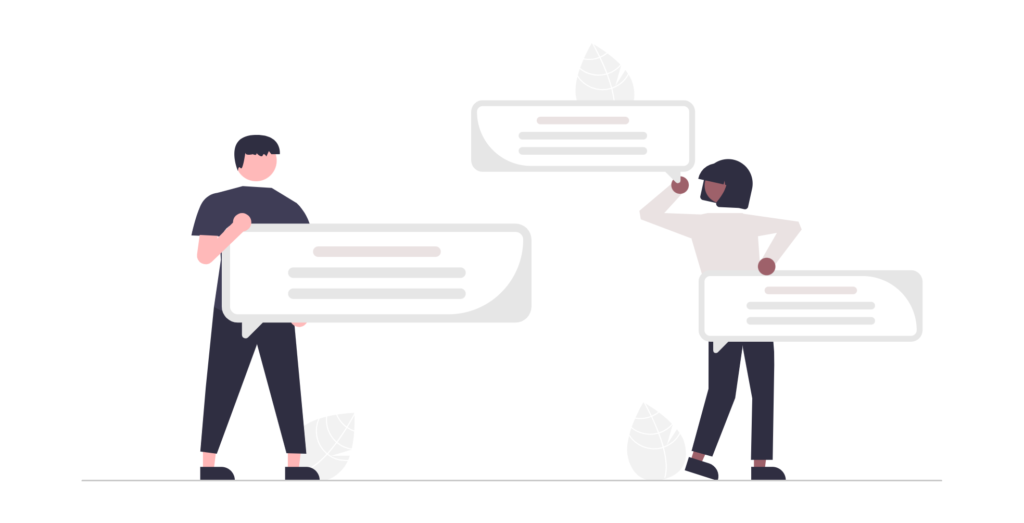
犬種によって、いびきをかきやすいかどうかには明確な傾向があります。
ポメラニアンの特徴も含めて見ていきましょう。
いびきをかきやすい犬種とは?
| 犬種分類 | 特徴 | 該当犬種 |
|---|---|---|
| 短頭種 | 鼻が短く気道構造が狭い | パグ、ブルドッグ、シーズーなど |
| 小型短マズル犬 | 鼻腔径が狭く、気道の余裕が小さい | チワワ、ポメラニアン、ヨーキーなど |
| 中~大型犬の一部 | 特殊な構造異常をもつ個体も | ボクサーなど交配種含む |
短頭種は顕著ですが、小型犬でも鼻腔の狭さや軟組織の影響で、いびきをかくリスクは高くなります。
ポメラニアンの特徴といびきのリスク因子
- 小型でマズルが短く、気道が狭い個体も多い
- 肥満になると首の脂肪が気道を圧迫しやすい
- 加齢とともに喉の筋力低下→いびきが出やすくなる
- 気管虚脱を起こしやすい犬種としても知られる
ポメラニアンは一見すると健康的に見えることもありますが、体の構造上、気道に関するトラブルを起こしやすい側面があるため、日頃から注意深く観察することが大切です。
犬のいびきは病院にいくべき?心配な症状まとめ

いびきは必ずしも異常とは限りませんが、「今までと違う」「他の症状もある」場合は注意が必要です。
ここでは、動物病院を受診すべきケースや、考えられる病態について整理していきます。
犬のいびきで病院に行くべき症状
- いびきの音が急に大きくなり、頻度も増えた
- 寝ているときに呼吸が止まりそうになる(無呼吸)
- 呼吸がゼーゼー・ガーガーして、苦しそうに見える
- 食事や水を飲むときにむせる・飲み込みづらそう
- 咳が続く、舌が青くなる(チアノーゼ)、失神したことがある
- 元気や食欲がなくなり、体重も減ってきた
これらは、呼吸器の異常や重篤な病気のサインである可能性があります。
いびきだけでなく他の症状が複数見られる場合、迷わず動物病院を受診しましょう。
犬のいびきの病態別解説まとめ
| 病態 | メカニズム | 主な症状 |
|---|---|---|
| 軟口蓋過長症 | 喉の奥にある軟口蓋が長すぎて、気道を物理的に塞ぐ | いびき、ガーガー音、興奮時の呼吸困難、チアノーゼ |
| 外鼻孔狭窄 | 鼻の穴が狭く、生まれつき空気の通りが悪い | 鼻づまり、フガフガ音、くしゃみ |
| 気管虚脱 | 気管が潰れやすくなり、呼吸時に空気の通りが妨げられる | 乾いた咳、ガーガー音、運動後の呼吸苦 |
| 咽頭虚脱 | 咽頭部(喉の入口)が呼吸時に内側へたわんでしまう | いびき、呼吸音の異常、無呼吸に見えることも |
| 腫瘍(鼻腔・咽頭・喉頭) | 空気の通り道にできた腫瘍が気道を狭くする | 呼吸困難、鼻血、片側の鼻水、くしゃみなど |
| アレルギー・上気道炎 | 粘膜の腫れ・炎症で気道が一時的に狭くなる | 季節性のくしゃみ、鼻水、いびきの増加 |
| 心疾患(二次的影響) | 心臓の異常が肺や気道に圧をかけ、呼吸が乱れる | 浅く速い呼吸、咳、倦怠感、失神など |
いびきの背後には、構造的な要因だけでなく、病的な変化や慢性疾患が隠れていることもあります。
特に「急な変化」や「症状の重なり」は見逃さないようにしましょう。
犬のいびきを軽減する対策や日々の観察
- 寝るときの姿勢を工夫(横向きや首の位置が下がらない体勢)
- 肥満傾向がある場合は、段階的な減量や食事管理を検討
- ハウスダストや花粉など、アレルゲンを減らす工夫をする
- 室温・湿度を一定に保ち、乾燥や刺激を防ぐ(加湿器も有効)
- 咳や呼吸音の変化、いびきの強弱などを記録しておく
観察とケアは飼い主にできる最初のステップです。
ただし、いびきに他の症状が併発したときは、自己判断せず早めに動物病院へ相談することが大切です。
【Q&A】犬のいびきに関するよくある質問
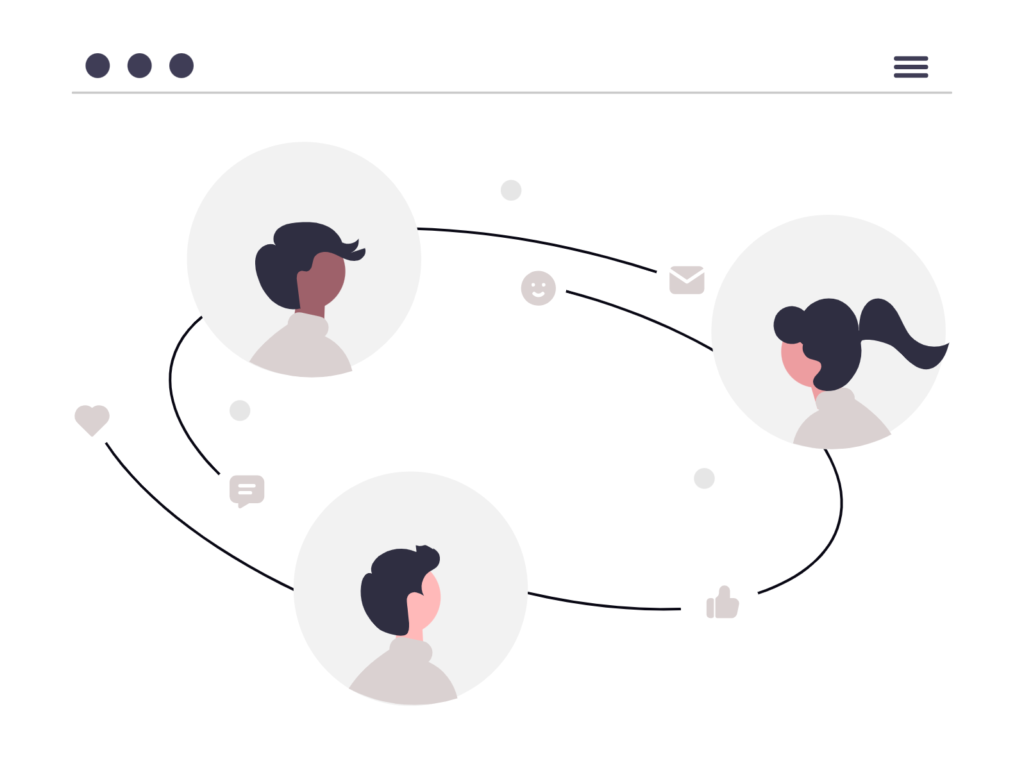
最後に、実際によくある飼い主さんの悩みをQ&A形式で解説していきます。
Q1:犬のいびきがうるさい…眠れないんです。
A:犬のいびきが大きくて眠れない場合、構造的な問題に加えて肥満や睡眠姿勢が関係している可能性があります。
寝る場所や体勢の調整、体重管理が改善のポイントです。
Q2:犬のいびきのような呼吸は病気?
A:日中に「いびきのような音」がある場合は、気管虚脱や呼吸器炎症が進行している恐れがあります。
咳や呼吸困難を伴う場合は早めの受診をおすすめします。
Q3:犬が寝てるときに鼻がピーピーなるのは大丈夫?
A:寝ているときに鼻がピーピー鳴るのは、鼻腔内が狭い・鼻水で通りにくいなどが原因です。
一時的であれば問題ないですが、繰り返す場合は鼻炎などを疑いましょう。
まとめ:犬のいびきは異常の見極めが大切
犬のいびきにはまず「解剖学的特徴」が大きな背景として関わりますが、肥満、炎症、加齢、重篤な呼吸器疾患などが引き金になり得ます。
ポメラニアンを含む小型犬では、急変や併発症には特に注意を払い、いびきの“変化”を見逃さないことが肝心です。
気になる点があれば獣医師の診断を仰ぎつつ、日常観察を習慣化して愛犬の呼吸の安心を守りましょう。